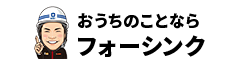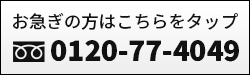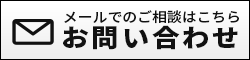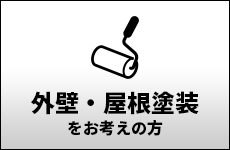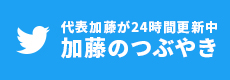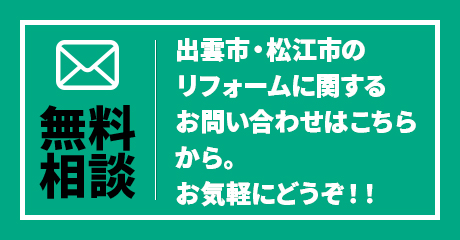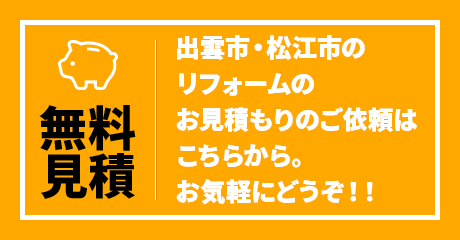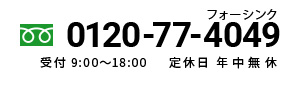バリアフリーに設けられている基準とは?
投稿日:
カテゴリー:建築士のリフォームお役立ちブログ
バリアフリーという言葉を頻繁に聞くようになって数年が経ちますが、そのバリアフリーの定義についてご存知の方は少ないのではないでしょうか。
今回は、バリアフリーに設けられている基準についてやバリアフリーの住宅を新たに建てる際のポイントをご紹介します。

バリアフリーの基準は、「建築物移動等円滑化基準」や「建築物移動等円滑化誘導基準」などによって定められています。
建築物移動等円滑化誘導基準では、以下のような規定を満たしているものをバリアフリーであると定めています。
・出入口の幅:玄関出入口120cm以上・居室出入口幅90cm以上
・廊下幅:180cm以上
・傾斜路:両側手すり・スロープ幅150cm以上・スロープ勾配1/12以下
・エレベーター:出入口90cm以上、かごの奥行135cm以上、かごの幅160cm以上、乗降ロビー180cm角以上
これらは、建物の入り口や廊下、内部に設けるエレベーター等について設けられた基準で、厳格にこうでなければいけないと定められているわけではありませんが、車いすの方でも過ごしやすいように配慮された区画であるといえます。

バリアフリーの戸建てを新築する際、まず考えなくてはならないのが動線をしっかりと整えることです。
特に、生活に欠かせない水回りの設備への動線は寝室から近い方が利用しやすいのは明白でしょう。
同時に行き止まりを無くし、回遊性のある間取りにすることで車いすの方の方向転換によるストレスを低減することが可能です。
将来的に車いすを使う可能性がゼロだと言い切ることはできないため、頭に入れておくと良いでしょう。

これは当たり前のことですが、できるだけ階段や段差を減らすというのがバリアフリーの基本です。
頻繁に通過するドアの部分は段差を無くしたり、スロープを設けたりすることで移動しやすいように設計することが大切。
2階建ての場合は、エレベーターを設けるか、踏面の幅・蹴上の高さをよく考えて設計する必要があります。
エレベーターの取り付けは後からリフォームで行うことも可能なため、事前に設けない場合はそのことも想定したうえでの間取り設計にすると良いでしょう。

今回は、そもそもバリアフリーの基準とは何なのかや、バリアフリーの戸建てを新築する際のポイントをご紹介しました。
文中でお話したように、将来的には自分自身が車いすを使用するかもしれないということを考慮して、ゆとりのある間取り設計を行えると良いでしょう。
今回は、バリアフリーに設けられている基準についてやバリアフリーの住宅を新たに建てる際のポイントをご紹介します。

□バリアフリーの基準とは?
バリアフリーの基準は、「建築物移動等円滑化基準」や「建築物移動等円滑化誘導基準」などによって定められています。
建築物移動等円滑化誘導基準では、以下のような規定を満たしているものをバリアフリーであると定めています。
・出入口の幅:玄関出入口120cm以上・居室出入口幅90cm以上
・廊下幅:180cm以上
・傾斜路:両側手すり・スロープ幅150cm以上・スロープ勾配1/12以下
・エレベーター:出入口90cm以上、かごの奥行135cm以上、かごの幅160cm以上、乗降ロビー180cm角以上
これらは、建物の入り口や廊下、内部に設けるエレベーター等について設けられた基準で、厳格にこうでなければいけないと定められているわけではありませんが、車いすの方でも過ごしやすいように配慮された区画であるといえます。

□バリアフリーの戸建てを新築するときのポイントをご紹介します!
*動線を重視した間取りを考える
バリアフリーの戸建てを新築する際、まず考えなくてはならないのが動線をしっかりと整えることです。
特に、生活に欠かせない水回りの設備への動線は寝室から近い方が利用しやすいのは明白でしょう。
同時に行き止まりを無くし、回遊性のある間取りにすることで車いすの方の方向転換によるストレスを低減することが可能です。
将来的に車いすを使う可能性がゼロだと言い切ることはできないため、頭に入れておくと良いでしょう。

*階段や段差を減らす
これは当たり前のことですが、できるだけ階段や段差を減らすというのがバリアフリーの基本です。
頻繁に通過するドアの部分は段差を無くしたり、スロープを設けたりすることで移動しやすいように設計することが大切。
2階建ての場合は、エレベーターを設けるか、踏面の幅・蹴上の高さをよく考えて設計する必要があります。
エレベーターの取り付けは後からリフォームで行うことも可能なため、事前に設けない場合はそのことも想定したうえでの間取り設計にすると良いでしょう。

□まとめ
今回は、そもそもバリアフリーの基準とは何なのかや、バリアフリーの戸建てを新築する際のポイントをご紹介しました。
文中でお話したように、将来的には自分自身が車いすを使用するかもしれないということを考慮して、ゆとりのある間取り設計を行えると良いでしょう。